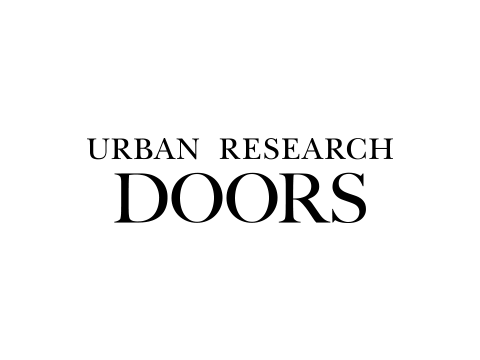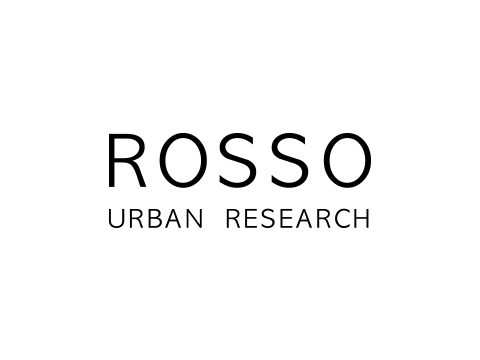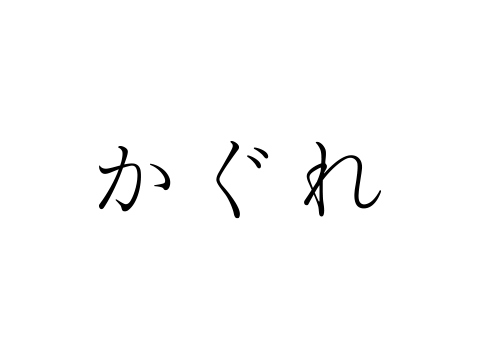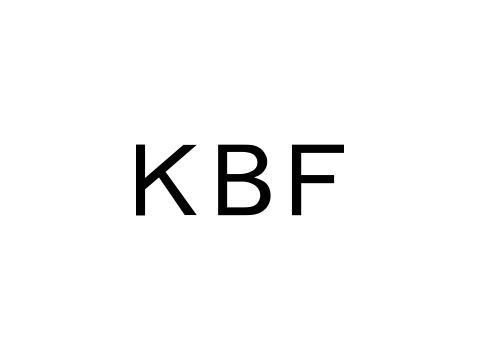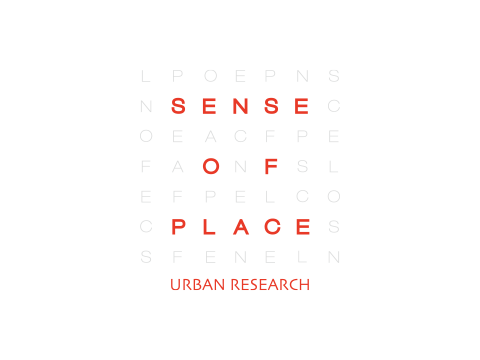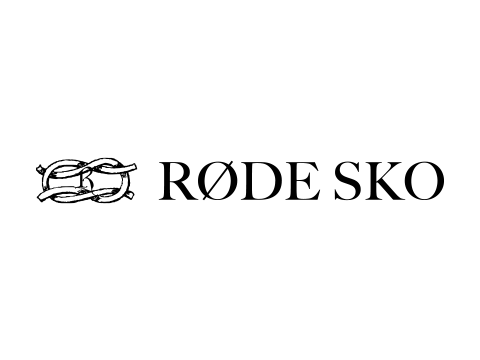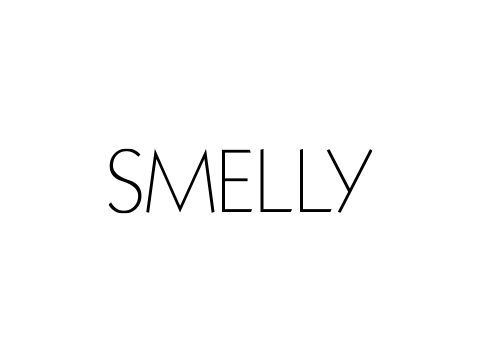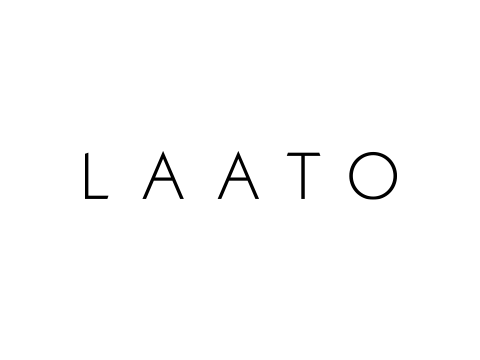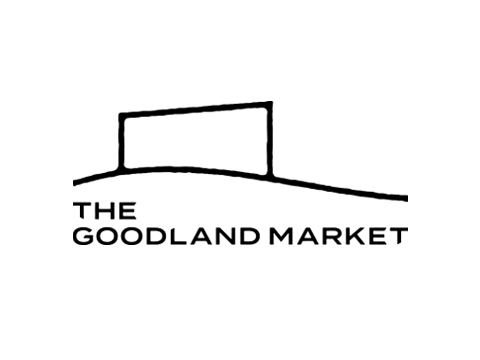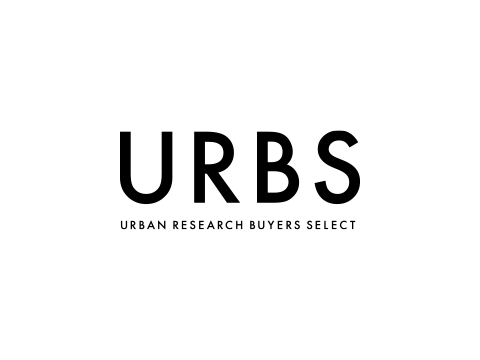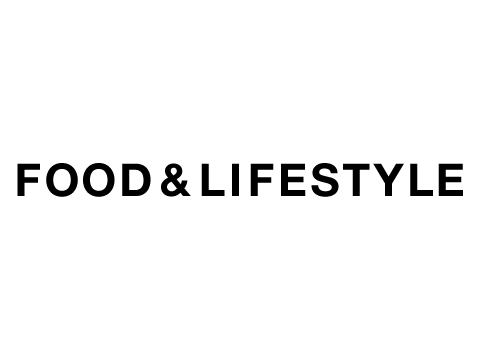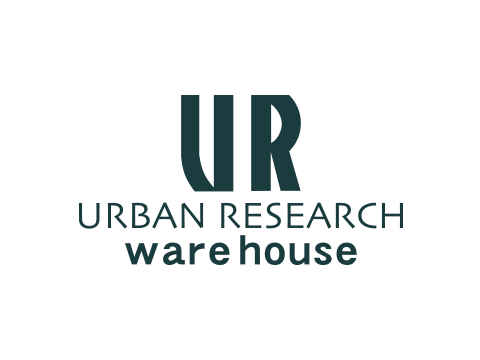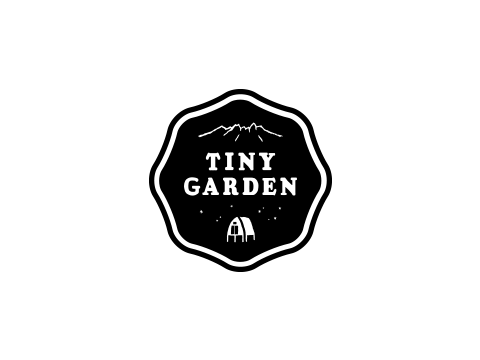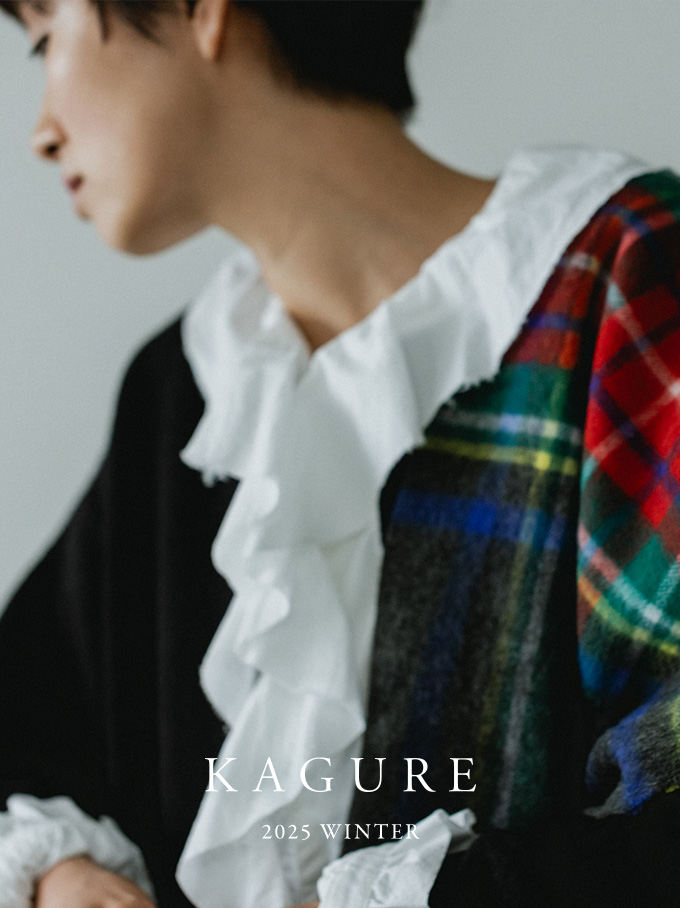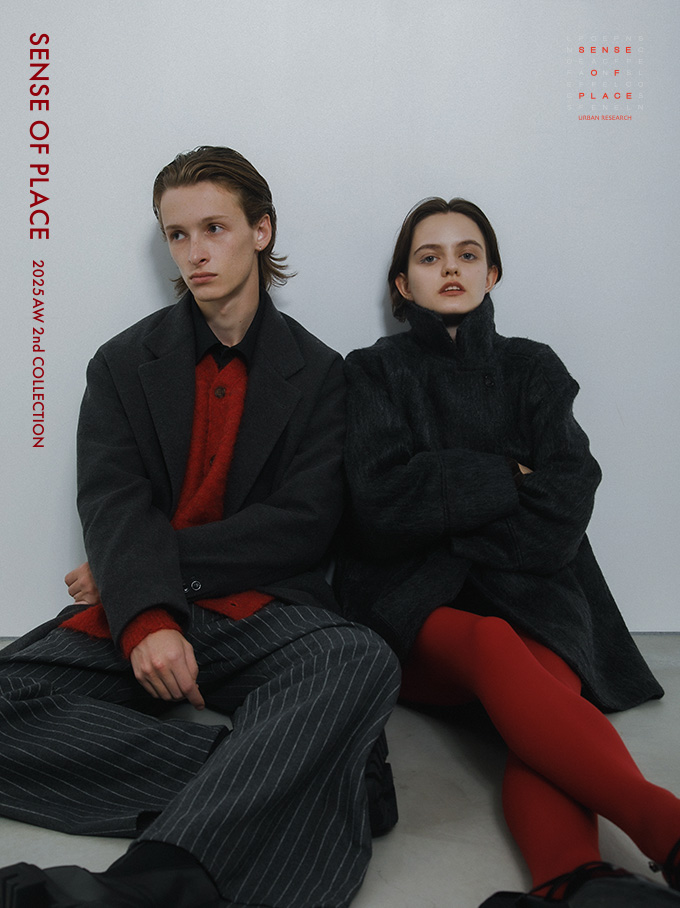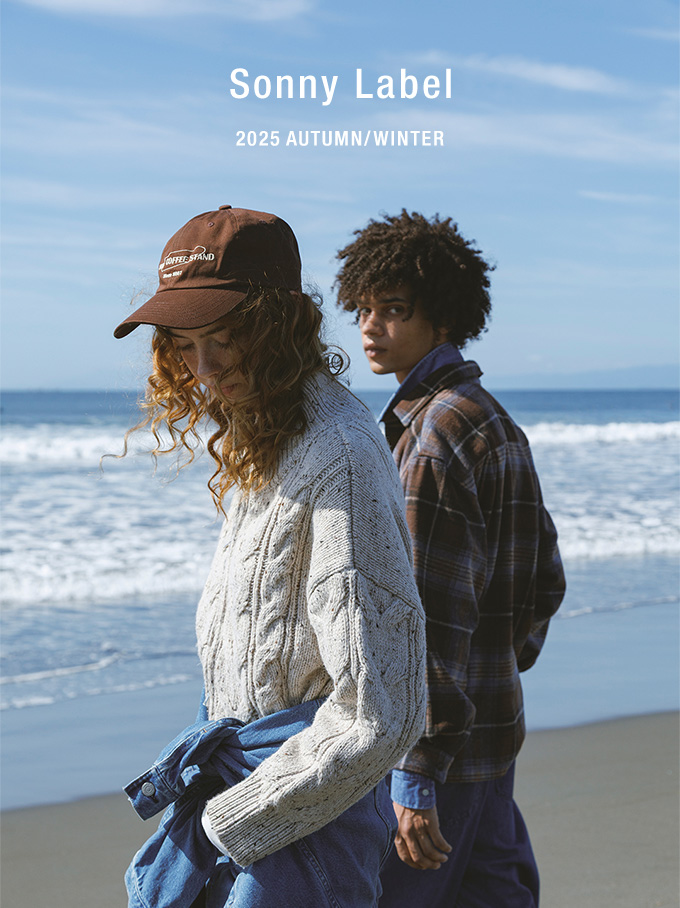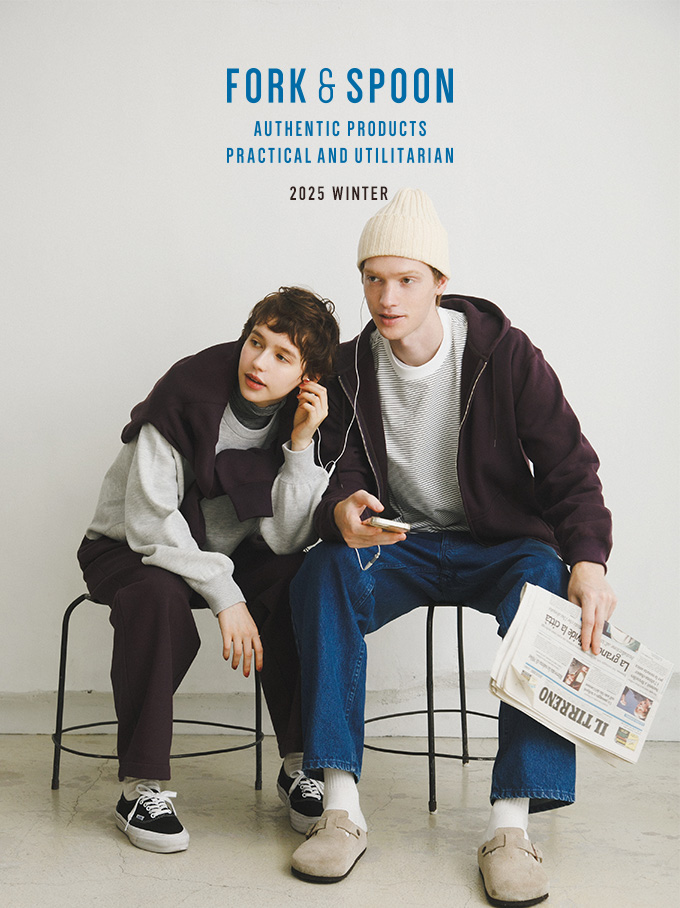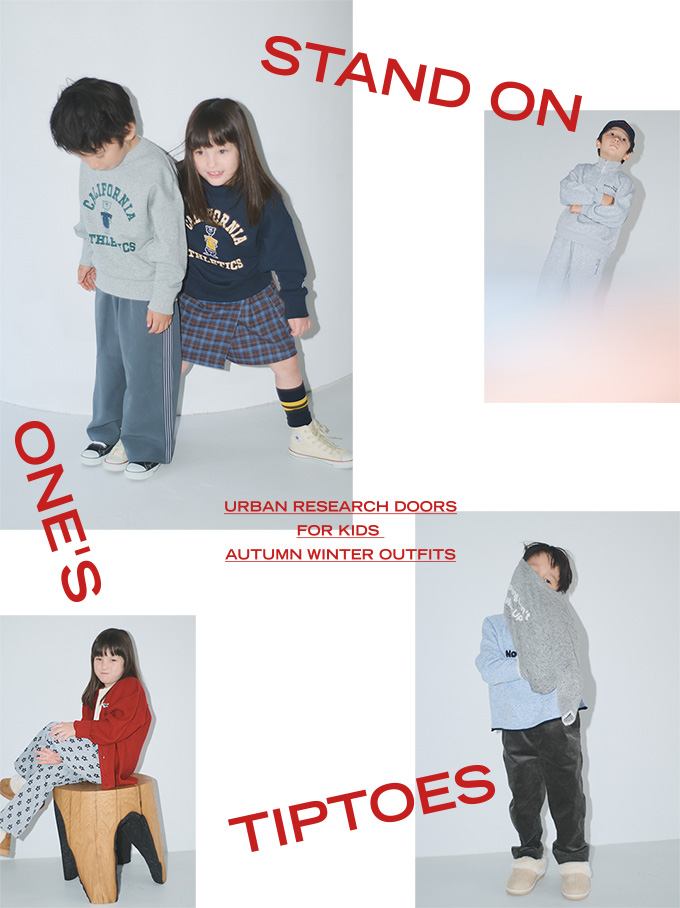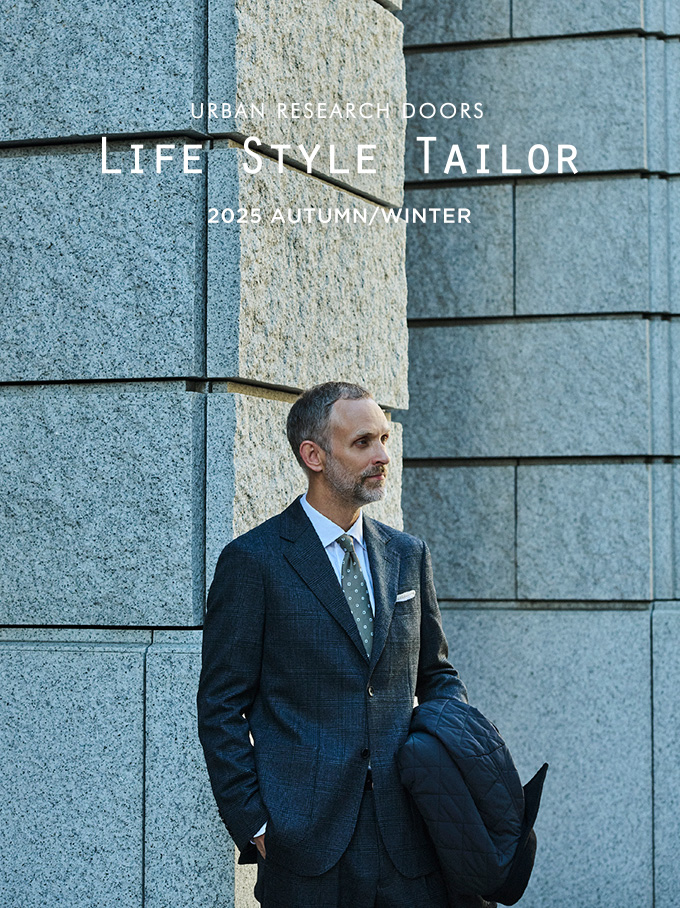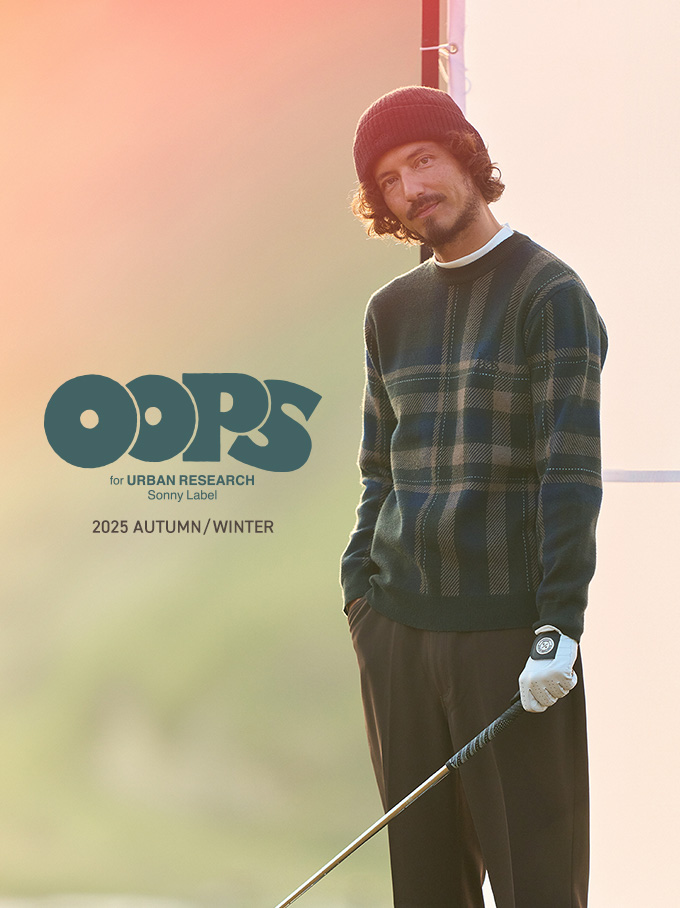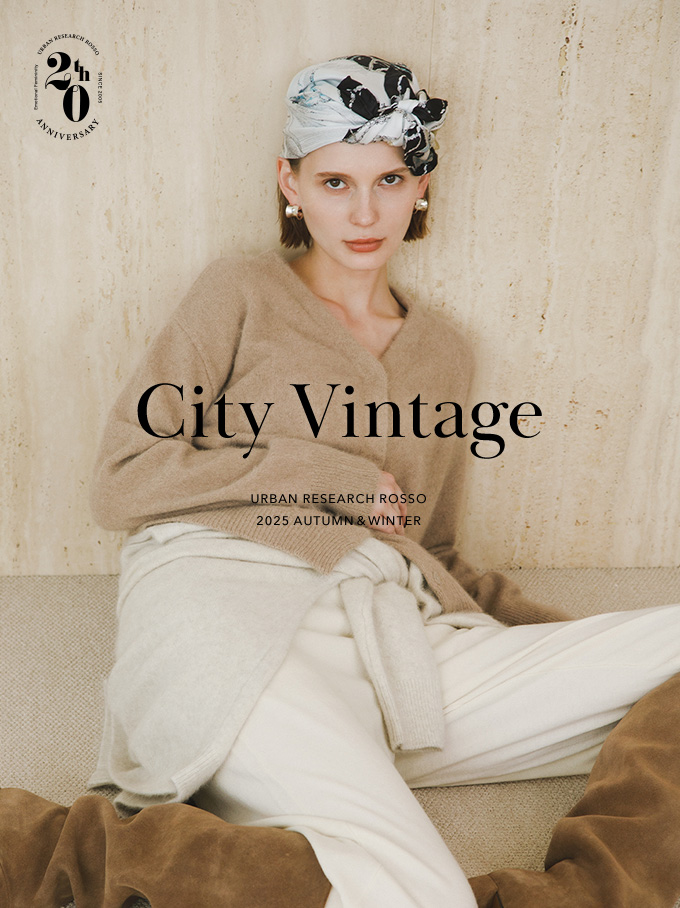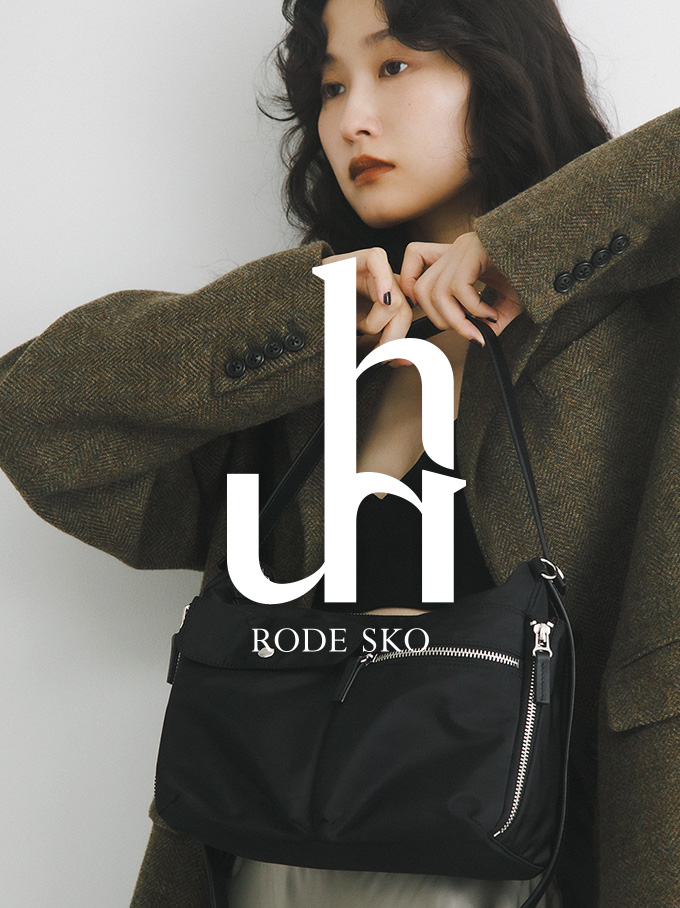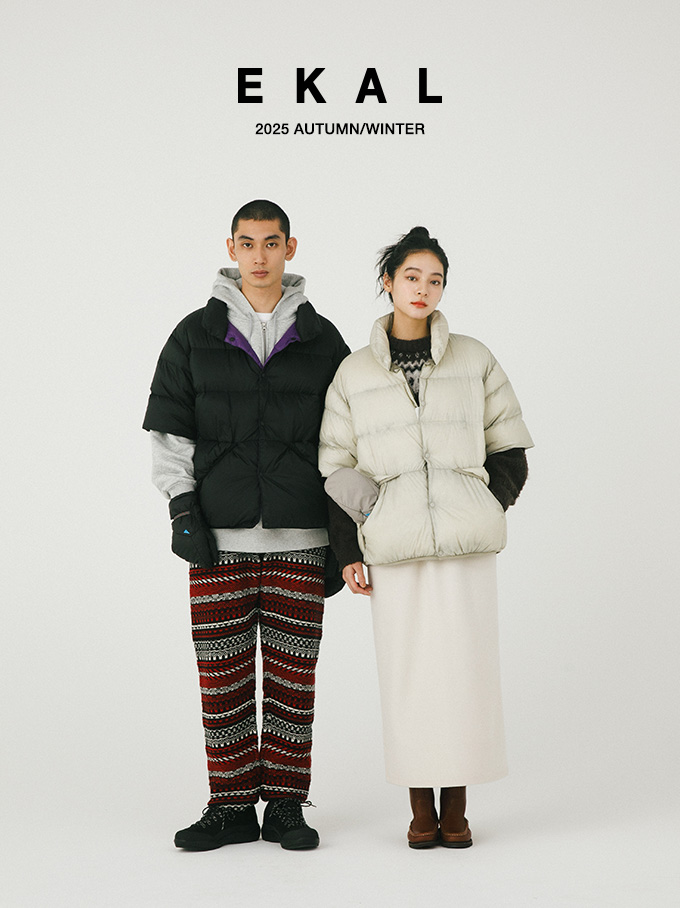【Old to the New, New to the Old 石巻】美味しい魚を届けるフィッシャーマン②

魚を獲る人がいる。そしてそれを食べる私たちがいる。そしてその間には、その魚を<もっと美味しく>してくれる人がいる。“神経締め”で魚のポテンシャルを最大まで高めるすごい人をご紹介します。
必殺仕事人!? 神経締めの達人

次にご紹介するのは、必殺仕事人…じゃなかった、必殺必中で魚の神経を締める「神経締め」のスペシャリスト、株式会社ダイスイの大森圭さん。
技法としては昔からあるものなのですが、最近特によく耳にすることの多い「神経締め」。ワイヤーなど特殊器具を用いて魚の鮮度を長く保てると言う技法です。なので釣り人などが独自に練習したり、それを動画でアップすることも増えて一般にもその名称が広がりつつあります。
魚の種類によって多少の違いはあるそうですが大まかにこのような手順を行うそうです。
脳を壊す(脳殺)、血抜きをする、神経を締める、(氷水などに浸して)冷しこみをする、温度管理のもと梱包する
脳を壊した時点で魚は脳死状態です。そこから血を抜いたり温度調整をしたり神経を締めるのは、死後硬直状態を遅らせるため。“死んだ”という信号が全身に駆け巡ると、魚が持つ美味しい成分がどんどん消費されたり内臓にいた寄生虫が身に移動してきたりしてしまうとか。

なので、死んでいるけれど、体には死んでいると悟らせない。そんな技なのです。大森さんはこれを「お手当て」と読んでいるそうです。

ふと、大森さんが神経締めをして抜いたワイヤーを「舐めてみます?」と差し出してきました。
思わずみんなで顔を見合わせます。その時に私たちの脳内によぎったのは「ものすごく生臭いんじゃないか…」。
「えっ美味しい」
勇気を出してファーストバイトに挑んだカメラマンのその声に押されて奪い合うように舐めてみました。
編集長がポツリ、
「魚のバタームニエルの味がする」
大げさでも冗談でもなく本当にそんな味。
その後いろんな魚の神経(髄液)の味を試させてもらったのだけれど全部味が違うし、全部美味しい。旨味がぎゅっと詰まっている。
髄液がこれだけ美味しいのだから身の方もさぞや…。

大森さんは今では全国のレストランや料理店から「大森式の魚が欲しい」と言わしめるほどの人ですが、鈴木さん同様「親の跡を継ぐなんて考えず」に東京や札幌でやんちゃしていた人です(やんちゃ具合も聞いたけどここでは割愛)。ですが30歳手前ふらりと石巻に戻ってきます。
実はやんちゃ以前に少しだけ市場で働いていたそうですが、その時に「漁師に価格決定権がない」ということに驚いたそう。そして実際石巻に戻ってきても変わらずに価格は市場が決める、大量に安く買う、という旧態依然の流通に呆れたそうだ。
大森さんに影響を与えた一人に横浜で料理人をしている人がいるのですが、その人からも「魚をもっと丁寧に扱えば、価値は上がる」と言われ、「なら漁師と手を組んで、いいものを納得のいく価格で流通させれば食べる人も幸せになれるんじゃないか」。
震災前からそんなことを考えていた大森さんは、震災後の混乱の中、自分が信じた方法をやってみようと思ったそうです。
大森さんなりの方法を始めたところ「問い合わせが増えて、美味しかったと言ってもらえたんです。この仕事楽しいかも、間違っていなかったと思えるようになりました。この前の3月11日にその横浜の料理人と飲んだのですが、その人にも“やってることは間違ってなかったな”と言ってもらえました」
大森さんの主な仕事は「仲買人」。市場や時には漁師から魚を買い付けて様々な場所に卸すお仕事。ですが大森さんは船にも乗っちゃうし、卸した先(料理屋など)にも足を運んで味をチェックします。
「最近スズキが揚がったのですが、これは本当は夏の魚。この時期は身の中にパワーがないはずなのにさばいてみたら身も美味しそうで脂もある。漁師に聞いたら黒潮に乗ったイワシを追いかけて北上してきた迷子のスズキだということがわかる。中間業者はそれをちゃんと次の人に伝えることが大事なんです。
卸先のお店に食べに行くのも、漁師、自分の手当て、そして職人の仕事、それが全部繋がっているのを確かめに行きたいから」
多くの神経締めでは「この魚種ならこう」とある種のコツみたいなものがあるのですが、大森さんはそうやって種類でカテゴライズするのではなく、魚1匹1匹に対して向き合います。それは卸先のお店に届く時間だけでなくその魚を調理する時間まで計算に入れたいからなんだとか。時には大森さんから「この魚がおすすめだよ」と料理やさんに直接営業の電話をすることも。だから(魚種ごとの)データを取ることはしない、という。

「料理で言えば出汁を引くみたいな感覚です。素材の反応を全部確かめて、時には冷やす温度を変えたり。もちろん失敗だってあります。時には料理さんにも教えてもらいながら、今日締めたこの1匹も新しいインプットにしたい」
また神経締めだけでなく「活魚トラック」という生きたまま魚を運べるトラックを乗りこなして、鮮度のいい魚を届けることもしています。
そんな風に手間のかかる作業が入るので、その魚の価値はぐんと上がります。
一般の流通とは逆らうように「いいものをきちんと高く買って、良い処理をして高く売る」ので、漁師さんからの信頼も厚く、厚くなれば良い魚を仕入れることにつながります。
そして最終的に私たちの口に入るときには「ポテンシャルの一番高い」状態。
いろんな意味でWIN-WINの関係を築いています。
もちろんこういった作業をすべての人ができるわけではないし、大森さんだからこその方法かもしれませんが「いただく命」を極限まで価値を高め、ひいては石巻の魚の価値をも高めています。

そんな大森さんの愛ある仕事ぶりに憧れた、TORITON PROJECT(トリトンプロジェクト)出身の新人仲買人がいます。
群馬県出身の吉岡祐亮さんはまだ25歳。以前は鮮魚売り場で働いていたんだそうです。漁師に憧れはじめは漁師への弟子入りを希望していたのだそう。ですが大森さんと出会ったことで、その仕事ぶりに魅了され、弟子入りします。

今日仕入れた魚はなんですか?と聞くと、「これは干物にするとおいしくて」「これよりもこっちが高級で」など次から次へと魚の紹介が始まります。大森さん同様の魚愛がすギョい!! ちなみに石巻の魚で何が一番好きか聞くと「アンコウ」なんだとか。
大森さんは「この仕事は氷山の一角のニッチなところにある。でもそれを深めていって地方で増えれば増えるほど業界が強くなる」と言います。
吉岡さんのように大森式を学ぶ若者が増え、そして大森式の魚を評価するお店が増えることは美味しい魚が好きな人にとっても大きなこと。

今回はそんな大森さんの魚に惚れ込んだ、石巻にある名店<いまむら>にもこれからお邪魔してきます。このお手当てされたお魚たちがどんな風に仕上がるのか。魚たちを眺めながらゴクリと喉がなりました。
最後に、日本が誇る「石巻漁港(石巻市水産物地方卸売市場)」へも足を運んでみました。

以前の、東洋一とうたわれていた水揚棟は震災で崩壊してしまいます。その後、仮設テントでせりを続ける姿は何度かテレビでも取り上げられ記憶にある人も多いですよね。
ですが平成27年、高度衛生管理対応型施設として再び建築されました。
底引き網や定置網など様々な漁法で獲られた魚が集まるので、種類も多種多様。

新しい魚市場では、2階からせりを見ることができる見学コース(要予約)もあります。ひろーい場内には大小様々な魚の入った箱が並び、あっという間にそれが競り落とされていきます。
この日フィッシャーマン・ジャパンのメンバーである鮮魚屋を営む津田祐樹さんがせりのために市場にきていたのでいろいろ教えてもらいました。
せりには地方ごとに独自のルールがあるそうで、石巻では手やりと呼ばれる指の動きで競り落とすものと、紙に希望価格を書いて入札するものと2種類あるそうです。
またせりも「下げぜり」と呼ばれる値段が徐々に下がるせり方法が主流なんだとか。
「ものによって値段が上がる時もあるから慣れていないと上がっているのか下がっているのかわからないんですよ(笑)」




その後、「もうすぐ船が着くよ」と教えていただいたので船着場にも行ってみました。
遠くに見えていた船があっという間に岸につき、大きな網で魚がどんどん移されていきます。
今回は「主に加工品に使われる」種類だったので取り扱う量もものすごく多く、一つの箱の大きさは子供が2、3人は入れるプールのようなサイズでした。こんなにも大量の魚を見たことはないので圧倒されます。

ちなみに取材に行った2月から3月にかけてはこれでも海流の関係で漁獲高は少ないシーズン。4月になればいろんな魚がどんどん集まるそうです。ぜひその時期に見学に行ってみてください。
普段おいしく食べてる魚がどんな人が獲っていて、どんな風に全国に行き渡って行くか、知ったことでまた一層おいしくいただくことができます。

私たちも帰る前に市場に併設された斎太郎食堂で海鮮丼を食べて、改めて身も心も魚愛に満たされたのでした。


石巻魚市場

フィッシャーマン・ジャパン
URL:https://fishermanjapan.com/
水産業の未来をつくろう。一緒に。「TRITON PROJECT」 : http://triton.fishermanjapan.com/
水産業特化型求人サイト「TRITON JOB」 : https://job.fishermanjapan.com/
3/24までクラウドファンディングに挑戦中! 「海の仕事を知り、海につながる場所をつくって、漁師を増やしたい!」 : https://camp-fire.jp/projects/view/130948


松尾 彩 Columnist