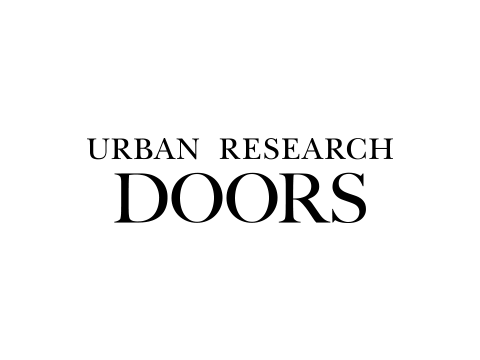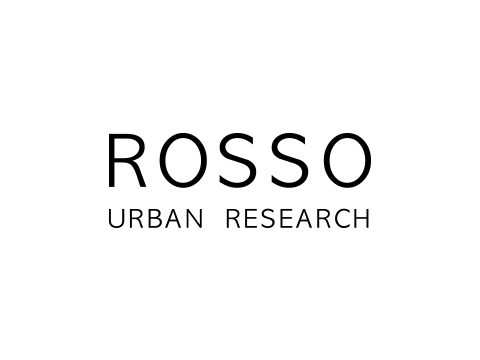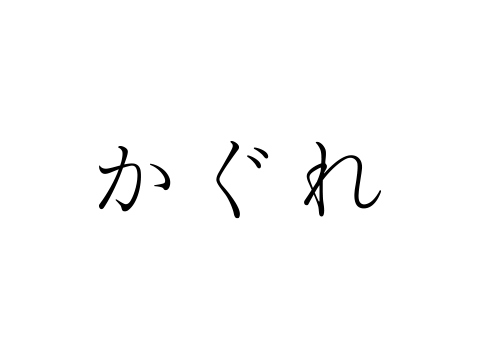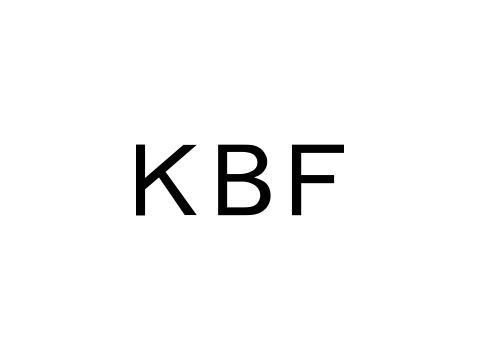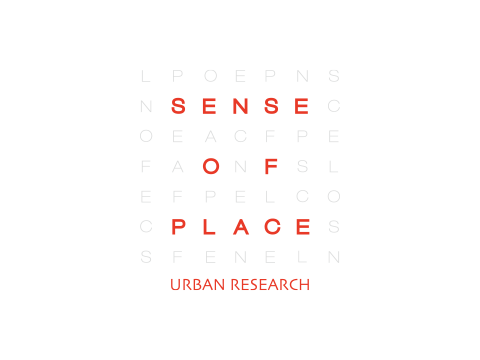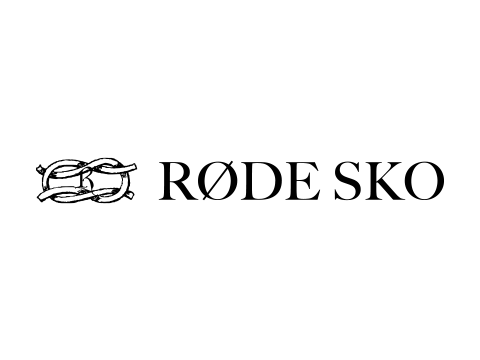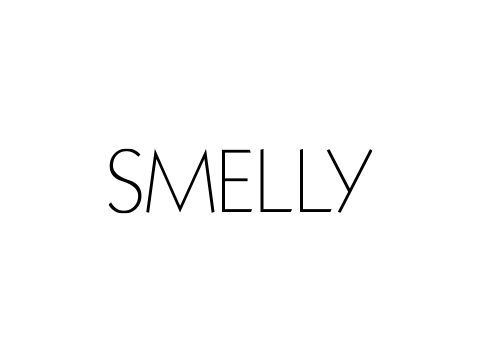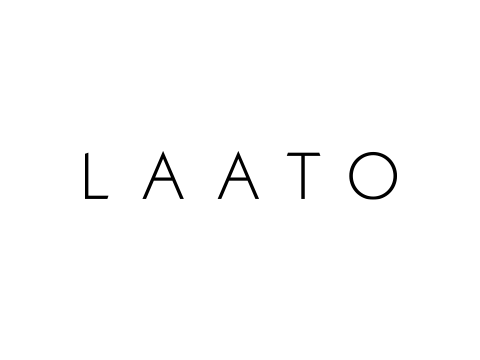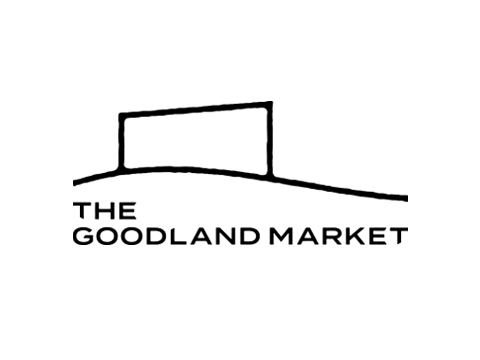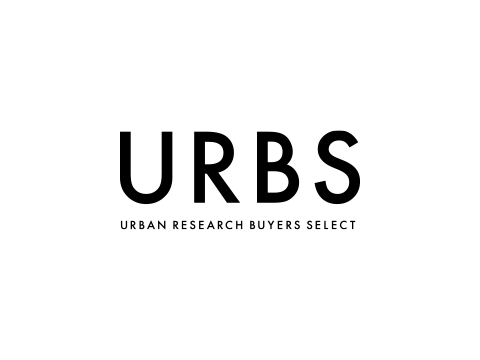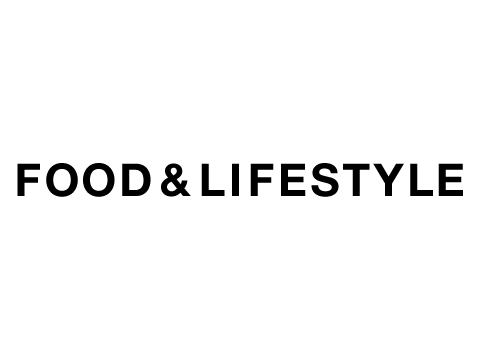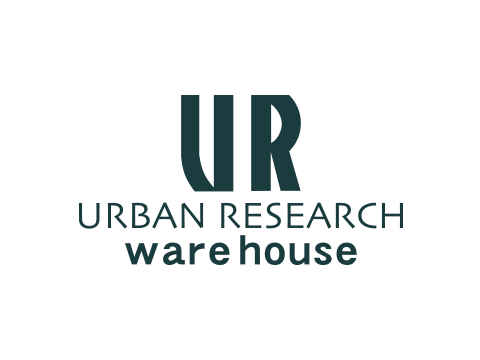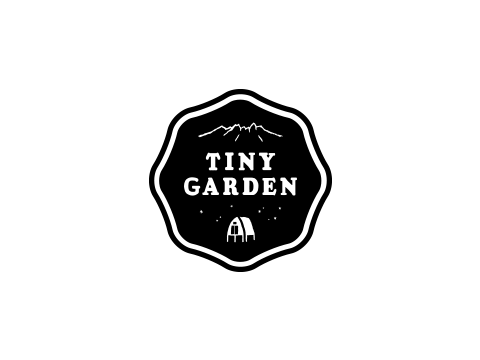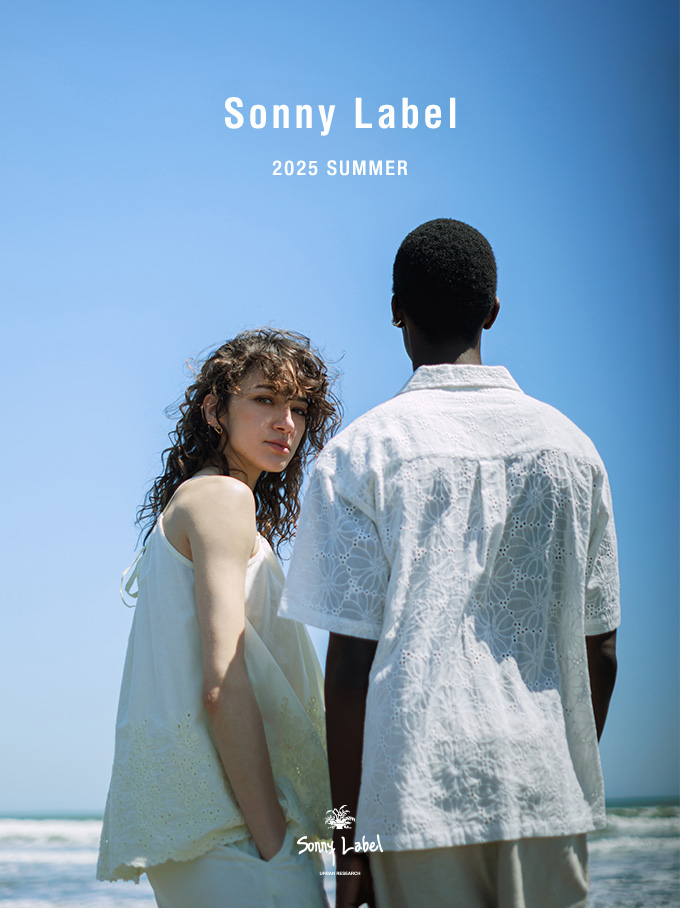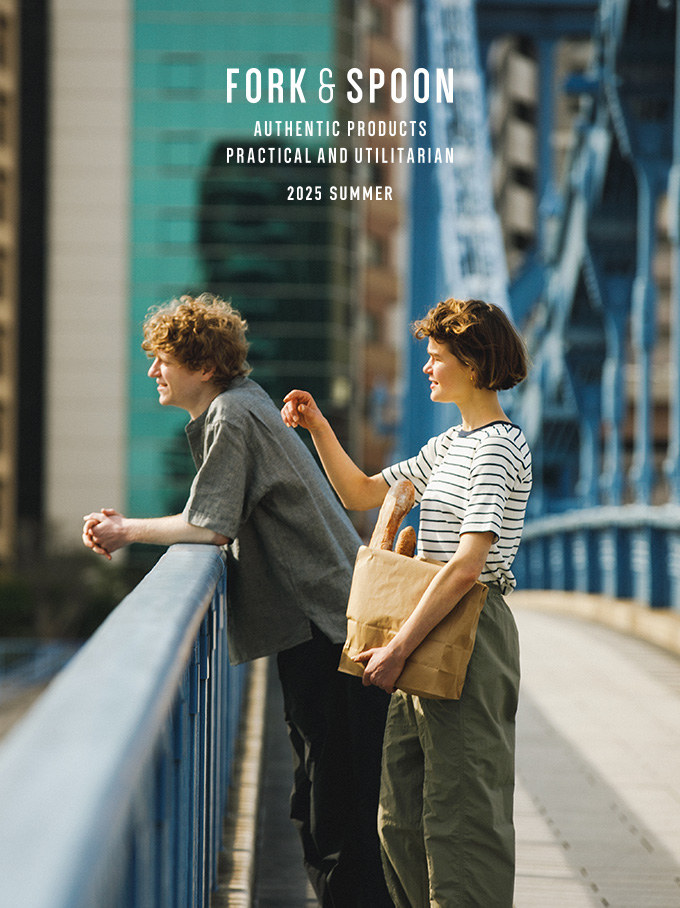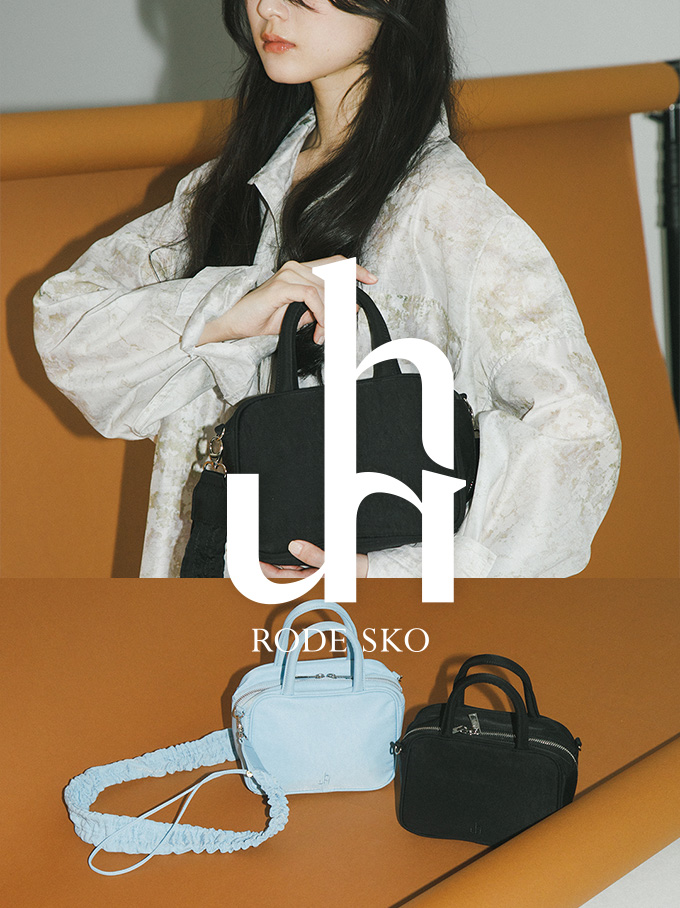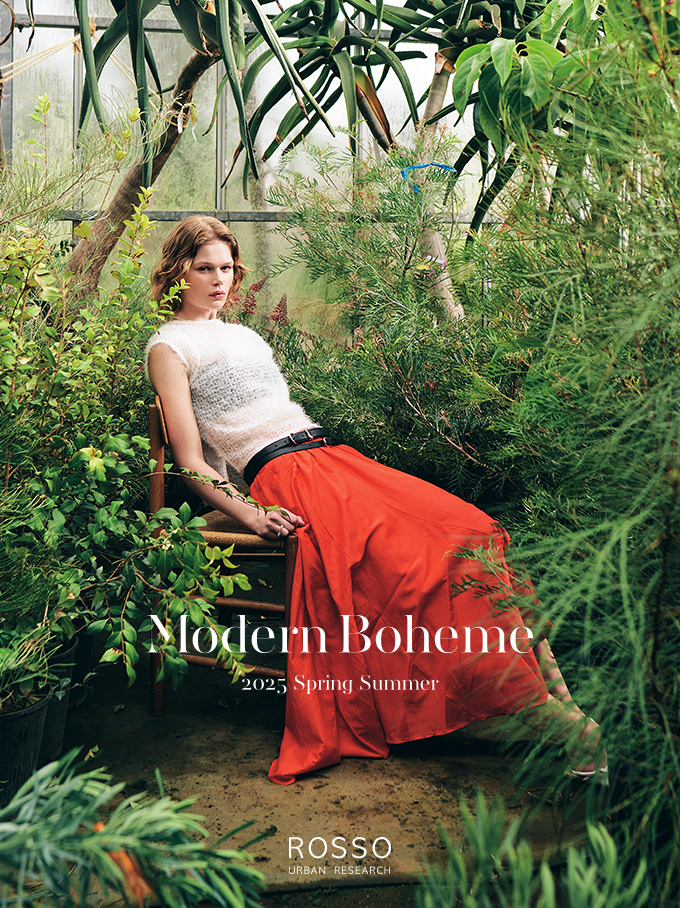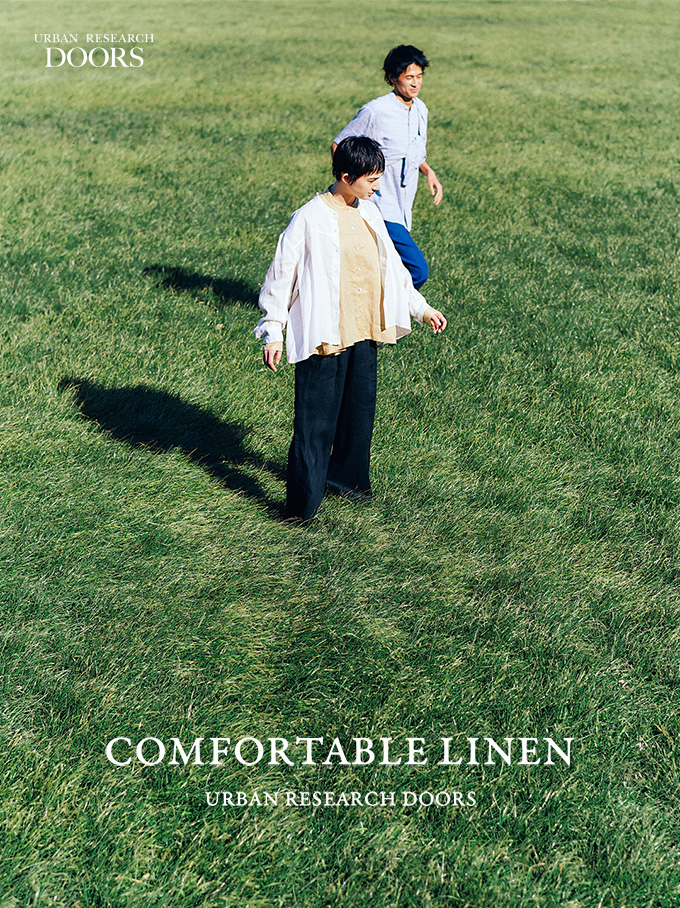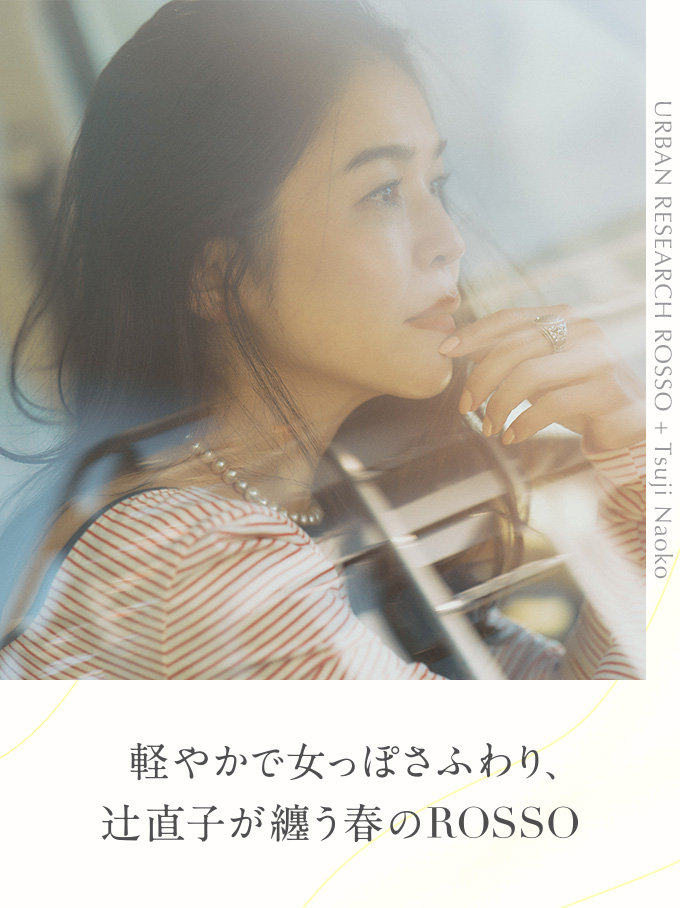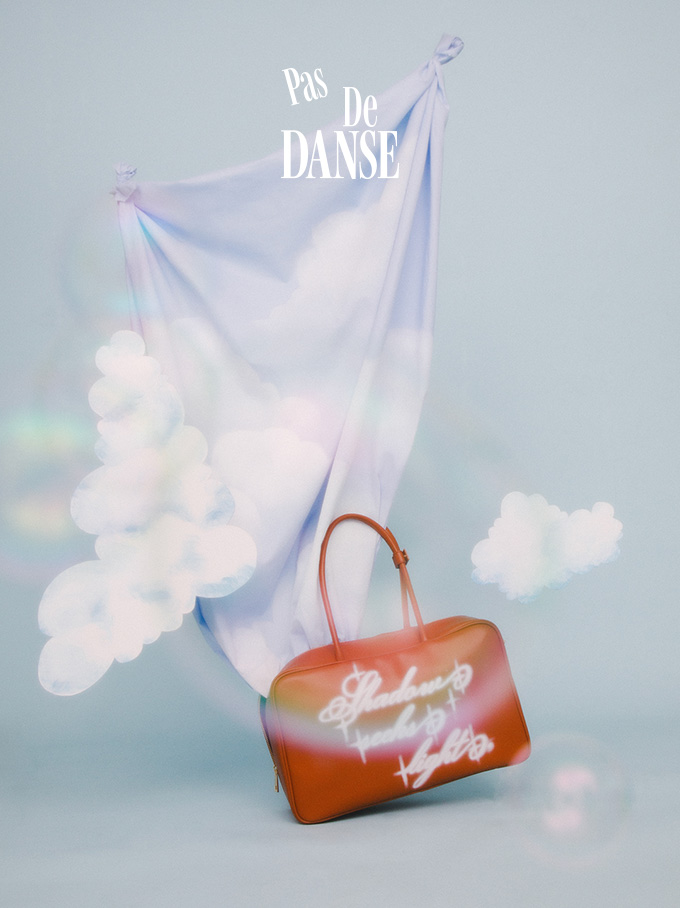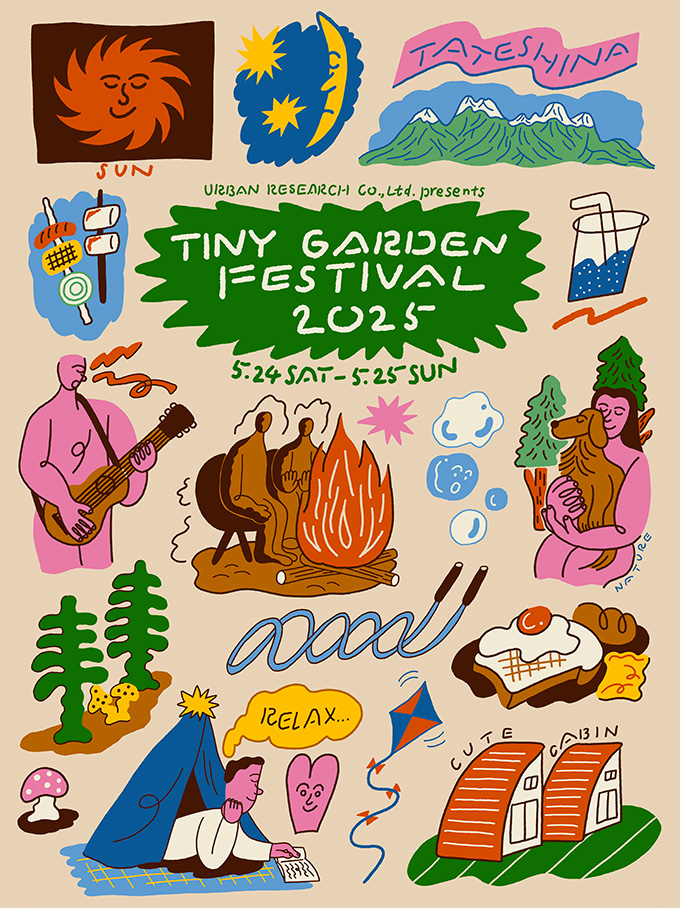【なんかイイ、荻窪】第二話 ターコイズにて。

通勤や通学で人はある程度決まった法則で線を描く。でもその中に時々、イレギュラーに動く線がある。それはたまの旅行だったり、お気に入りのお店へ行く動線だったり。荻窪駅前には、たくさんの人から繰り返し伸びる線が重なってできた、濃密な<点>があった。第二話 ターコイズにて。
荻窪 午後11時。
街を俯瞰で眺め人々の動きを<線>とすると、どの街にもその線が急に濃く重なるところがある。駅ビルなどの大容量の建物だけでなく、“常連”を抱えるお店もまたしかり。
荻窪にはチェーン店も多いけれど、街の規模の割に個人店もとても多い。仕事終わりに、帰宅途中に、そして家の近所だからとそれぞれのタイミングで、お気に入りのお店へと荻窪界隈の人たちの線は伸びてゆく。
大きな駅ビルをはじめ、たくさんのお店が集結する荻窪には“働くため”にここへやってくる人も多い。彼らも仕事終わりに荻窪でそのまま夜ご飯を食べたりちょっと飲んだりすることも多いけれど、いつかは自分の住む街へと帰途につく。
さて、そこから本来の住人が羽根を伸ばす時間帯がやってくる。
午後11時ごろ、荻窪にいる人はそうやって入れ替わる。
アダチにも仕事を終えたあと、ひと息つく店があると言う。

ターコイズ。

駅そばのクラフトビールのお店だ。
小さな迷宮のような駅前の路地を入ったところにある。
ビールといえば、最近若者のビール離れが進んでいると聞いたことがある。
理由の一つは、お酒自体飲まなくなったこと
一つはビールの味が好きではない、という人が多くなったこと。
だけれどこのお店には若者も非常に多かったのに少し驚く。(もちろん、見るからにビール好きのおじさんも多い)
すっかり日本でも定着しつつある<クラフトビール>だけれど、実はきちんと説明するのはちょっと難しい。大まかなイメージは、「大量生産ではなく、丁寧に作られた」ビールだろうか。
日本の法律上、「ビール」と名がつくものは指定された副材料を使う。
それ以外を使った場合名称は「発泡酒」になるので、クラフトビールの中でもフルーツを使ったりすると扱い的には発泡酒になるそうだ。ちょっとややこしい。
さらにアメリカでは「小規模や地元密着」「伝統的な手法」などの明確なルールがあるけれど、実は日本ではそこまでのきちんとしたルールはないことも説明をややこしくさせる。また<クラフトビール>の名前が定着するまでに広まっていた<地ビール>という名称と、意味はイコールなのか、そうでないのか。それもまた確実にルール化したものはない。
ただ<クラフト>とはつまり職人技的なものである。だからざっくりとだけれど「丁寧に」「個性的に」作られたものがクラフトビール、といった認識で間違ってはいないはずだ。

いずれにせよクラフトビールの多くは丁寧に、独自の材料を使って作られる。
したがって大手メーカーの量産型ビールに比べれば価格も高い。
例えばターコイズでもおよそ1杯の価格は1000円前後。安いチェーン居酒屋の生ビールが500円もしないことを考えると倍以上の値段だ。
彼ら(若者)のお財布事情からすればそこそこ高級な値段にもかかわらず、しかも若者の味覚離れが噂されているビールなのにもかかわらず、若い世代すら虜にしている。
毎夜、その味を求めて客は途絶えない。
若者すら虜にしているのは、その味なのかこの店の雰囲気なのか。
それを確かめたくてオープン直後から終電ギリギリまでカウンターの端っこをキープして、ビールを飲みながら仕事おわりに合流するアダチを待つ。と言うのを数日繰り返した。
ビールのつまみに店主の重田さん(シゲちゃん)の話を聞きながら。

個人的なクラフトビールとの最初の思い出は、ロンドンのパブだったが、実はそんなに味は印象に残っていない。
なぜならパブ特有の賑やか過ぎる(酒好きの雰囲気はだいたいどの国だって同じだ)空間や、酔ってますます聞き取りづらくなる英語、そして<中>サイズが日本の特大サイズで出てくることもありあっという間に酔ってしまって、味など覚える暇もなく。ただ日本のキンキンに冷えたビールとは違って、なんだか生ぬるく、小麦の味が強いなあ、パンを飲んでいるようだ。そんな思い出だけが残っている。
さて、ターコイズならありがたいことにメニューは日本語で、尋ねれば店主のシゲちゃんが特徴などを詳しく答えてくれる。
ロンドンのパブ以来妙に苦手意識のあったクラフトビールに、ゆっくりと向き合うことができた。

瓶のビールも置いてあるが、ここでの人気は樽から注ぐフレッシュなやつ。常時7種類の生ビールが楽しめる。
樽がなくなり別の銘柄に交換するので、たいてい1週間くらいで違う種類に変わるという。瓶も含め、その多くが知らなかった種類のものばかり。
例えばこんな感じだ
・伊勢角屋麦酒/ヒメホワイト/度数5%…オレンジピールの代わりにゆずの皮を使い、天然酵母の香りを引き立てる優しい和のスパイス感をもった、伊勢のホワイトエール
・南信州ビール/アップルホップシナノスイート/6.5%…南信州で栽培されたりんごをジュースにして使用。スムースで飲みやすいフルーツビール。
・いわて蔵ビール/ヴァイツェンボック/7%…濃厚な味わいのヴァイツェン。公募由来のフルーティ感とクローブを思わせるスモーキーな香りにしっかりとしたコクとのバランスが絶妙。
などなど。
アダチを待つ間、その7種類のうち、3種類ほどを飲んでみた。
並べれば小麦色から琥珀のような色味までまずは見た目も様々。もちろん味も違う。甘みが強い奴、苦味が強い奴、様々なフルーツやスパイスの香り。そしてワインのように飲み始めののどごし、ふた口目、3口目と印象がどんどん変わる。
もちろん個性的なものばかりなので、一口目が好みに合わないものもあった。だけど不思議なことに「なんだろうこの味は?」と確かめるように飲み進めると、気がつけば「美味しかったなあ」と味覚も変化していく。
ちなみにシゲちゃんに初めてクラフトビールを飲んだ時のことを聞くと、その感想は、“とても衝撃的”だったそうだ。
それは<美味しすぎて>の衝撃では、ない。
「その時は恵比寿のクラフトビールの店に連れて行ってもらったんですが、炭酸がなくて、ぬるくて…。“なんじゃこりゃ”って正直最初まずかった(笑)。でも徐々にはまっていったんですよ。
ちなみにここでお店を始めた当時も、お客さんの反応は同じく“なんじゃこりゃ”か“ビールなのに高くない?”でした(笑)。でもそういう人ほど2、3種類飲むとはまるんです。たくさんの種類があるので、その中から好みを探すのが面白いし、それこそ飲んでみないと(好みの味が)わからないし」
そんな風に、最初はクラフトビールに“なんじゃこりゃ”だったシゲちゃんがすっかりクラフトビールにはまってしまったきっかけの1杯は<コエドの伽羅Kyara>だったそうだ。
コエド(COEDO)は川越にあるクラフトビールの会社。
伽羅はとてもフルーティなラガーだ。コエドはサツマイモを原料にしたクラフトビールで一躍有名になった。ラベルデザインもすっきりとしていてそれこそワインのように香りや風味を楽しめるものが揃う。
先述のようにクラフトビールは「地ビール」と呼ばれることも多いが、それは川越をはじめとした日本各地で作られていることが多いことにもあり(つまりは“地のもののビール”的な意味合いで)、それもまた魅力の一つになっている。
「各地の醸造所に行くのも楽しんです。試飲させてくれるし(笑)。だいたい行きづらいところにあるんですよね。水がとてもいい宮崎の山奥とか。だから旅行がてら訪ねて歩いています」


ちなみにアルコール度数も幅の広いクラフトビールだが、度数は発酵時間(糖の濃度)によるものなのだそう。例えばワイン並に長い年月をかけて熟成させる<バーレーワイン>は度数が12、3度ほど。味はみたらしだんごみたいなんだそうだ。みたらしビール…気になる。

ちなみにターコイズはつまみも美味しい。
看板メニューはジャークチキン。
コンビニで売っている多くの大手の缶ビールと比べて(比べるものでもないけれど)味わい深い分、おつまみもパンチが効いたものがあう。
例えばニンニクの効いた枝豆、スパイスの香り高いジャークチキン、メニューにはチリコンカンもあった(ちなみにフードメニューはちょくちょく変わるそうだ)。
メニューにはハンバーガーも並ぶ。これがまた相当美味しいそうだが、ビールでお腹いっぱいになるので毎回ハンバーガーまでたどり着いたことはない。いつか食べようと思いつつ飲んだことのないクラフトビールの味が気になりすぎて結局食べられないのだ。


そうこうしているうちに、仕事を終えたアダチ来たりて。

苦味が強烈で飲みごたえのあるIPAビールが好きだと言う彼は、メニューの中からさっと好みに合いそうなものを選ぶ。シゲちゃんを荻窪の兄と慕うアダチは、ここで2、3ヶ月間ほどお店を手伝ったこともあるそうだ。その時に美味しい注ぎ方や美味しいおつまみのレシピ教えてもらったとか。
「コンビニで買う缶ビールもいいけど、生の方が風味が豊か。クラフトビールは最初の泡を捨てて、基本泡少なめに注ぐのも特徴なんだよね。お店によっては泡を完全にカットすることもあるって」
などシゲちゃん仕込み(?)のクラフトビール豆知識を教えてくれるアダチ。
そんな話をしていると、アダチの顔見知りが来店し隣の席に着く。彼もまたターコイズの常連で、三鷹にすんでいるそうだ。
「普段のアダチくんとライブのアダチくんは別人だよね。ここで知り合ってから1年位経つけど、最初はただの酔っ払いかと思ってたよ(笑)。でも歌っているのを見て「えっまじなんだ」って驚いた」と携帯の写真フォルダに入ったアダチのライブ写真を見せながらそんな話をしてくれた。




そういえば店内にもペドラザのフライヤーが貼ってあったりして、アダチの馴染み具合があちこちに感じられる。

「前に荻窪の居酒屋でバイトしていた時は、仕事終わりに週に2、3回ターコイズに来ていたかな。今はライブもあったりでもう少し頻度は低いけど、今でもここには来たくなる。確かに値段は張るけど、ここでしか飲めない味だし、“ご褒美”みたいなもの。
通っているうちに友達もできたし。最初はビールの好みとかの話から始まって、仲良くなるうちに荻窪の話や仕事の話をしたりして。
だから“誰かに会えたらいいな”と思ってここに来ることもある。誘うには時間も遅いし、急だけど、今日みたいにここに来れば誰かいたらラッキーだし、誰もいなくてもシゲちゃんがいるし!」

お互い酔いの回った状態なので、同じような質問をし、同じような答えがかえってくる体たらくではあったけれど、その中でなんどもアダチが「居心地が良い」と繰り返すのが印象的だった。
確かにここは居心地が良い。初めて来たけれどすっかり店に馴染んでしまったような錯覚さえある。
ここの居心地の良さはなんだろう。
と、同時に“そういえば何故大人になると自然と友達を作るのがけっこう大変になってくるんだろう”、なんて考えていた。
逆を言うと小学校時代、なぜあんなに簡単に友達ができたのか。隣の席になったら、同じクラスになったら、そんな簡単なことで友達になれていた時代が懐かしい。アダチの話を聞きながら、「教室のドアを開けたら誰かがいる」と言う安心感もすんなりと友達になれる雰囲気の一つだったことを思い出した。
そしてここにはその「誰かがいる」と言う安心感がある。
入り口のドアを開けたらすぐ、店の全貌が見渡せるのもとても良い。
誰かが入ってきたり、帰ろうとしているのがひと目でわかる。
また外から覗いて誰がいるかすぐわかったり。この日も外からちらっと店内を見て知り合いを見つけて嬉しそうに入ってくる常連客がいた。
もちろん最初から「友達を作ろう」とお店にくるわけではないけれど、気がつけば友達が増えていたという話を聞くと、ここでならあの小学校の頃のような自然な“友達100人できるかな”が叶う気がしてきた(給食の牛乳が、ビールに変わって)。
そんな風に居心地の良さと味覚の冒険を求めて今日もターコイズは満員御礼、なのであった。

CRAFT BEER STAND TURQUOISE (クラフトビアスタンドターコイズ)
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目4-9
営業時間 : [月~木]18:00~24:00
[金、土]18:00〜26:00
定休日:日曜・他不定休
URL:https://www.facebook.com/ogikubo.turquoise/